個人の町民税・県民税
[2025年12月26日]
個人の前年の所得などをもとにかかる税金で、均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担をしていただく所得割から成り立っています。個人町民税と個人県民税の申告と納付は、合わせて行います。
均等割・所得割共に課税の対象となります。
※その年の1月1日現在(賦課期日)に、町内に住んでいる人(住民登録がある人)が対象となります。
均等割のみの課税となります。
※町内に住所があるかどうか、また事務所があるかどうかは、その年の1月1日現在(賦課期日)の状況で判断されます。
町内に住民登録をしないで住んでいる場合、住民登録地と二重課税が発生するおそれがあります。このような不都合を避けるため、住民登録は必ず居住地にしてください。
町民税・県民税の税額は、均等割と所得割の2つからなり、その合計額が税額となります。
所得割額は、次のような方法で計算されます。
株式譲渡所得割額・配当割額控除のうち税額控除できなかった額のある人については、期別の先頭から順次充当され、充当後の残金額をお支払いいただくこととなります。充当後も株式譲渡所得割額・配当割額控除額が余る場合は、余った金額を還付する通知を後日お知らせします。
所得割額の計算の基礎となるもので、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算定されます。
令和8年度以降は以下のとおりです。
ここでは、所得金額調整控除に該当しない場合の例について案内します。
| 給与等の収⼊⾦額Ⓐ | 給与所得控除後の⾦額(所得⾦額調整控除前) | |
|---|---|---|
| 0円 〜 650,999円 | 0円 | |
| 651,000円 〜 1,899,999円 | 収⼊⾦額Ⓐ-650,000円 | |
| 1,900,000円 〜 3,599,999円 | 収⼊⾦額Ⓐ÷4=Ⓑ (※千円未満切り捨て) | Ⓑ×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円 〜 6,599,999円 | Ⓑ×3.2-440,000円 | |
| 6,600,000円 〜 8,499,999円 | 収⼊⾦額Ⓐ×0.9-1,100,000円 | |
| 8,500,000円 〜 | 収⼊⾦額Ⓐ-1,950,000円 | |
下記に該当する場合は、給与所得控除後の金額から所得金額調整控除額が差し引かれます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
1.特別障害者に該当する
2.年齢23歳未満の扶養親族を有する
3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除={給与等の収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%
(2)給与所得控除後の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除={給与所得控除後の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円
ここでは、公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合の例について案内します。公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超の場合、計算方法が下記とは異なります。
| 公的年金等の収入額 | 公的年金等の雑所得 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0円 ~ 600,000円 | 0円 | |||||||||||||
| 600,001円 ~ 1,299,999円 | 収入金額-600,000円 | |||||||||||||
| 1,300,000円 ~ 4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | |||||||||||||
| 4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | |||||||||||||
| 7,700,000円 ~ 9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | |||||||||||||
| 10,000,000円 ~ | 収入金額-1,955,000円 | |||||||||||||
| 公的年金等の収入額 | 公的年金等の雑所得 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0円 ~ 1,100,000円 | 0円 | |||||||||||||
| 1,100,001円 ~ 3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 | |||||||||||||
| 3,300,000円 ~ 4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | |||||||||||||
| 4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | |||||||||||||
| 7,700,000円 ~ 9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | |||||||||||||
| 10,000,000円 ~ | 収入金額-1,955,000円 | |||||||||||||
納税義務者の扶養親族・社会保険料など個人的な事情を考慮し、実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くことをいいます。所得控除の種類と控除額は次のとおりです。
AとBのいずれか多い金額
支払った医療費の金額-保険金などで補てんされる金額-総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか少ない金額
※控除限度額 200万円
支払額の全額
支払額の全額
前年中にご本人や配偶者、その他の親族が受取人となる生命保険契約により、支払った生命保険料等がある場合、保険会社等の控除証明書が必要です。(旧生命保険料に係るもので1契約9千円以下のものを除きます。)
支払った保険料の区分
| 支払った保険料 | 控 除 額 |
|---|---|
| 0円 ~ 12,000円 | 支払金額 |
| 12,001円 ~ 32,000円 | 支払金額×0.5+6,000円 |
| 32,001円 ~ 56,000円 | 支払金額×0.25+14,000円 |
| 56,001円 ~ | 28,000円 |
※それぞれの保険料控除の適用限度額は28,000円、合計適用限度額は70,000円です。
支払った保険料の区分
| 支払った保険料 | 控 除 額 |
|---|---|
| 0円 ~ 15,000円 | 支払金額 |
| 15,001円 ~ 40,000円 | 支払金額×0.5+7,500円 |
| 40,001円 ~ 70,000円 | 支払金額×0.25+17,500円 |
| 70,001円 ~ | 35,000円 |
※それぞれの保険料控除の適用限度額は35,000円、合計適用限度額は70,000円です。
新契約と旧契約の双方の支払保険料について一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、次の1または2の金額の合計額(上限28,000円)になります。
前年中にご本人や配偶者、その他の親族が所有している居住用建物または生活用動産を保険の目的とする地震保険契約等の保険料を支払った場合
保険会社等の控除証明書が必要です。
| 支払った保険料 | 控 除 額 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0円 ~ 50,000円 | 支払金額×0.5 | |||||||||||
| 50,001円 ~ | 25,000円 | |||||||||||
| 支払った保険料 | 控 除 額 |
|---|---|
| 0円 ~ 5,000円 | 支払金額 |
| 5,001円 ~ 15,000円 | 支払金額×0.5+2,500円 |
| 15,001円 ~ | 10,000円 |
支払った地震保険料(ア)により求めた金額+支払った長期損害保険料(イ)により求めた金額
※最高限度額 25,000円
ひとつの損害保険契約等が、地震保険契約と長期損害保険契約の両方の契約区分に該当する場合には、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして控除額を計算します。
26万円
(1)夫と離婚して再婚していない人で、扶養親族があり、合計所得金額が500万円以下の場合
(2)夫と死別して再婚していない(または夫の生死が明らかでない)人で、合計所得金額が500万円以下の場合
※ひとり親控除に該当する場合はひとり親控除を適用します。
30万円
配偶者と死別・離婚して再婚していない人や、配偶者の生死が明らかでない人で、総所得金額等58万円以下の生計を一にする子(他の納税義務者の控除対象配偶者や扶養親族とされていない)があり、合計所得金額500万円以下の場合
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外です。
26万円
配偶者・配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者を有する納税義務者で1年間(1~12月)の配偶者の所得金額に応じて、控除を受けることができます。
※事業専従者控除を受けられる方は、重複してこの控除を受けることはできません。
配偶者控除・配偶者特別控除一覧表
合計所得金額が58万円以下であり、他の方の控除対象配偶者・扶養親族・専従者に該当されない人に限られます。
※16歳未満の扶養親族を有する場合は、所得税の確定申告や町県民税の申告をする際に、申告書の該当欄へその旨を記入してください。また、給与所得者や公的年金受給者の人の場合は、扶養親族申告書を提出してください。
| 区 分 | 控 除 額 (1人につき) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般扶養 (16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満) | 33万円 | |||||||||
| 特定扶養(19歳以上23歳未満) | 45万円 | |||||||||
| 老人扶養(70歳以上) 同居の場合 | 45万円 | |||||||||
| 老人扶養(70歳以上) 別居の場合 | 38万円 | |||||||||
| 年少扶養(0歳以上16歳未満) | 扶養控除はありませんが、非課税判定の基礎人員数や障害者控除の対象となります。 | |||||||||
19歳以上23歳未満の親族で、他の人の控除対象配偶者・専従者に該当されない人に限られます。合計所得金額に応じて下記のとおり控除額が異なります。
| 特定親族の前年の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 580,000円 ~ 950,000円 | 45万円 |
| 950,001円 ~ 1,000,000円 | 41万円 |
| 1,000,001円 ~ 1,050,000円 | 31万円 |
| 1,050,001円 ~ 1,100,000円 | 21万円 |
| 1,100,001円 ~ 1,150,000円 | 11万円 |
| 1,150,001円 ~ 1,200,000円 | 6万円 |
| 1,200,001円 ~ 1,230,000円 | 3万円 |
| 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| ~ 24,000,000円 | 43万円 |
| 24,000,001円 ~ 24,500,000円 | 29万円 |
| 24,500,001円 ~ 25,000,000円 | 15万円 |
| 25,000,001円 ~ | — |
以下の団体等に対して行った寄附金については、個人住民税の税額控除を受けることが出来ます。
控除額の計算は以下のとおりです。
(寄附金(※1)-2,000円)×10%(※2)
(※1)総所得金額等の30%を限度
(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率より算出
(寄附金-2,000円)×(90%-0~45%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021(※3))
(※3)復興特別所得税分(平成26年度から令和20年度の税率に加算)
詳しくは、ふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
前年中の総所得金額等の合計が、次に掲げる額以下の人
| 税 目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
|---|---|---|---|
| 町県民税均等割 | 町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
| 県民税 | 2,000円 | 1,500円 | |
| 合 計 | 5,500円 | 4,500円※ | |
※令和6年度から、町県民税の均等割と併せて、森林環境税(国税)年額1,000円の課税が始まりました。詳しくは、「森林環境税(国税)について」のページをご確認ください。
新たに入社した従業員や、在職しているが、普通徴収(個人納付)で個人の町県民税を納付している従業員について、年度途中で特別徴収に変更する場合は「特別徴収連絡書」を提出してください。
納期の特例は、個人の町県民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合に、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
(納期限が土日祝日にあたる場合はその翌日が納期限となります。)
この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、申請により市町村長の承認を受ける必要があります。
特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合に「特別徴収義務者の所在地・名称変更等届出書」を提出してください。
各種様式
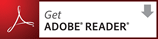

業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)